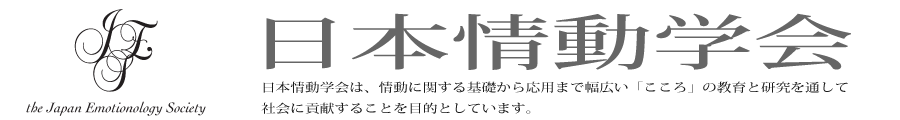日本情動学会理事長よりのご挨拶

近年、いじめ、キレやすい子供や自殺者の増加、残虐性のある少年犯罪、情動障害およびそれに基づく行動障害など「人間らしさ」の喪失が社会問題化しています。また、環境ホルモンや周産期障害に伴う脳の発達障害や小児の心理的発達障害(自閉症や学習障害児をはじめとする種々の精神神経疾患)、統合失調症患者の精神・行動の障害、さらには青年・老年期のストレス性神経症やうつ病の増加が社会問題化しております。これら情動や行動障害を伴う障害は、人間らしく日常生活を続ける上で重大な支障をきたし、本人にとっても非常に大きな苦痛を伴うだけでなく、深刻な社会問題にもなっております。
本学会は、日本や世界の将来を憂う研究者が集って、平成18年10月24日に「こころ」の理解を深めるというザブテーマでシンポジウムが開催され、情動研究会としてスタートしました。「こころ」の核心は喜怒哀楽の感情(情動)であり、ヒトの行動の基本原理をなしています。我々は、意識下、あるいは無意識的に相手の「こころ」の核心をなす情動を読み取ることで相手の行動を推測でき、大きな集団(社会)の中でも適切に行動することができます。ヒト(ホモサピエンス)では、他の種と比べこのような情動に中心的な役割を果たしている扁桃体の体積が増大しており、より大きな社会の中でも適切に行動できるよう進化してきた、さらには社会行動により人間社会が発展してきたと推測されております。一方、我々ホモサピエンスと同時代に生息していたネアンデルタール人の社会は極めて閉鎖的であり、そのために滅亡したと推測する研究者もいるようです。このように社会が存続していくためには、少なくとも情動が適切に機能している必要があります。
現代社会は益々複雑化してきており、それに伴いヒトの「こころ」やその核心をなす「情動」に対する関心が急速に高まっています。「情動」に関する科学的な解明は、医療現場や医薬学だけでなく、政治・経済、教育、理工学など社会のあらゆる領域から、より専門的で、より複雑化したニーズが生まれ、現代社会の要請であると考えられます。近年では、ヒトの情動や感情を分析し、窓口対応業務などでストレスを受けている方をサポートする「感情AI」も登場しています。2011年には、このような情動の仕組みと働きやその応用を「情動学」として科学的に体系化することを願い、情動研究会は日本情動学会として新たな一歩を踏み出しました。自然科学だけでなく、人文科学や社会科学を含む学祭的分野の方々が日本情動学会に参加され、「こころ」の情動学の体系化が進展することにより社会に貢献できることを願っております。
日本情動学会 理事長 西条寿夫(東亜大学特任教授、富山大学名誉教授)
日本情動学会副理事長ご挨拶
この度、副理事長を拝命いたしました。西条理事長のもと副理事長として日本情動学会の活動推進に貢献していきたいと存じます。また事務局も飛田の研究室内に置くこととなりましたので、事務局機能としてもお役に立てば幸いです。研究者となることを全く想像もしていなかった医学生が、なぜか大学卒業直後から生理学研究室に身を置くこととなり、当初は情動研究には程遠い分野での研究をスタートさせました。初代理事長の小野先生や西条先生と恩師西野先生との?がりのためなのか?これまたなぜか?研究生活の中で情動に関する研究テーマを展開することとなっております。
しかし最近では、医学・心理学・教育学など幅広い分野にまたがる情動研究は、“奥が深く”また“面白い”と考えております。さらには、ヒトが生きる上で、情動の理解は“最も重要なのではないか?”とも考え始めております。
この領域の研究の”面白さ“と重要さ”を、副理事長として皆様と共有し、さらにはより広めていくことに繋げていきたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。
名古屋市立大学・医学研究科・脳神経生理学 教授 飛田秀樹